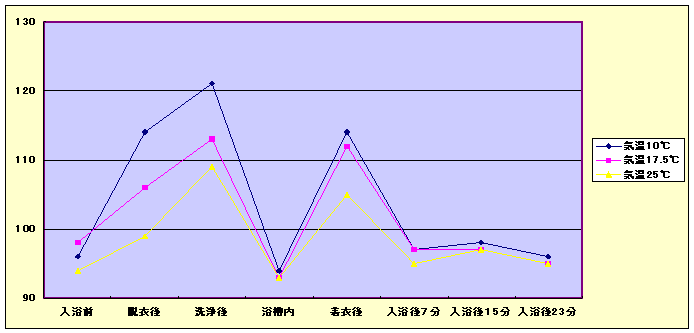
ライプロのホームページへようこそ!!
脳血管障害予防のための住宅リフォーム
室内温熱環境におけるバリアフリー計画
人口動態統計調査によると、月別全死亡率は、12月から3月の冬期間において高い数値を示している。
地域別に分けてみると、北海道地域については、年間を通して平準化を示す値となっているが、その他の地域は冬期間の死亡率が高くなっている。
北海道地域とその他の地域において、住宅内における温熱環境に大きな違いがある。
北海道地域においての住宅は、風除室等を設け外気の進入を防ぎ、冬期間の暖房は、住宅内すべての部屋に計画されており、温度差のない状態にある。
しかし、その他の地域においては、住宅内における各室別の個別暖房が主流であり、廊下、洗面、脱衣室、浴室等は暖房計画がされた住宅は少ない状態にある。
また、家庭内の不慮の事故で死亡する高齢者の割合は多く、また、その3分の1が浴室での溺死であったと言われている。
入浴中及び入浴後の死亡者数は、年間14,000人にも達し、この数字は交通事故による年間死亡者数を上回る。
入浴死は、12月から2月までの冬季に多く、しかも、高齢者の死亡が8割を占めている。
東京都監察医務院資料によれば、65歳以上の高齢者の入浴中の死亡原因の割合は溺死が1割で、循環器系疾患が6割、脳血管障害が2割である。この過半数以上を占める循環器系疾患も脳血管障害も、血圧が急激に変化することが原因となる。
冬季入浴に伴う血圧変動の例として下記にグラフを示しているが、脱衣室や浴室は暖房されることが少ないため、暖かい居間から脱衣室へ移動し、裸になり、寒さにさらされると、血圧が急上昇する。その上、熱い湯に浸かると、血圧は驚愕反射により再上昇し、脳出血を発症しかねない。さらには、冬季の風呂は熱い湯が好まれ、肩までお湯に浸かることが多いが、温熱効果により皮膚血管が拡張して血圧が逆に低下する。温まって発汗により脱水が生じると、血液粘度が増し、心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすくなる。
また、浴槽から出るために急に立ち上がると、血圧が急速に再低下し、失神することもある。
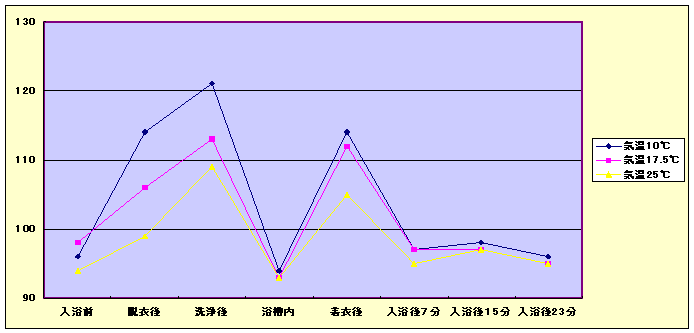
血圧調整能力が劣る高齢者では、こうした症状が発症しやすい。主要国の溺死率(ほとんどが入浴死による)を比較すると、明らかにわが国の溺死率は高く、特に75歳以上の後期高齢者の死亡率は20倍近く高い。高齢者が、いかに危険な入浴を行っているかが伺える。
また、死亡に至らなくても、脳血管障害により身体的機能障害の残った人数は、この数値の3倍から4倍はいると思われる。
入浴死を防ぐには、浴室・脱衣室の室温を上げること、すなわり暖房が不可欠である。従来の日本の住宅では、長時間滞在する居間や寝室に暖房が限られていたが、高齢社会を迎えた現在、浴室やトイレなどの小空間の設備にも注目すべきであると思われる。